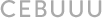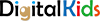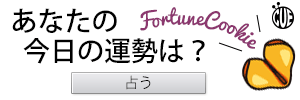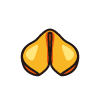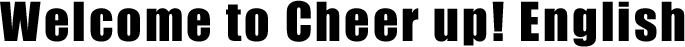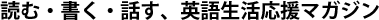Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
英語表現・フレーズ検索
フレーズデータベース検索
そして、最終的に衣裳の着物を着付ける人形着付け師のもとで、完成まで仕上げられる。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
一般によくいわれる、有職人形はこのような製作手順がとられている。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
市松人形
Ichimatsu ningyo
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
詳細は市松人形を参照されたし
Refer to Ichimatsu ningyo for details
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
木目込人形
Kimekomi ningyo (wooden dolls)
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
詳細は木目込人形を参照されたし
Refer to Kimekomi ningyo for details
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
おやま人形
Oyama ningyo
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
製法は衣裳人形に準ずる。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
風俗人形(ふうぞくにんぎょう)
Fuzoku ningyo
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
やまと人形
Yamato ningyo
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
市松人形、東人形、京人形 (人形)などの総称。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
各地でめいめいに呼ばれていたため、1933年(昭和8年)吉徳十世山田徳兵衛が中心となり、総じて「やまと人形」の呼称が考えだされた。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
頭と手足は桐塑、胴はおがくずを詰め込んだ布で出来た玩具の着せ替え人形で、人形のみでの状態で売られ、着物や衣装は購入者が作成する。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
御所人形(ごしょにんぎょう)
Gosho ningyo (Imperial palace dolls)
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
おもに男児の赤子、帝をかたどった土製、桐塑製の人形。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
江戸時代には、その見た目より白菊人形、頭大人形、人形問屋の名前より伊豆蔵人形とも呼ばれてた。
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス
Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス