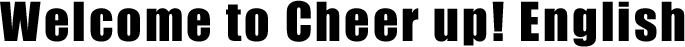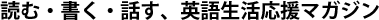"Ujidainagon monogatari (The Tale of Uji Dainagon (
chief councilor of state))," which was quoted
in "Kachoyojo," the
old notes
written by Kaneyoshi ICHIJO, states that Murasaki Shikibu's
father FUJIWARA
no Tametoki wrote
an outline of "The Tale of Genji" and had his
daughter Murasaki Shikibu
write down the details.