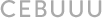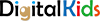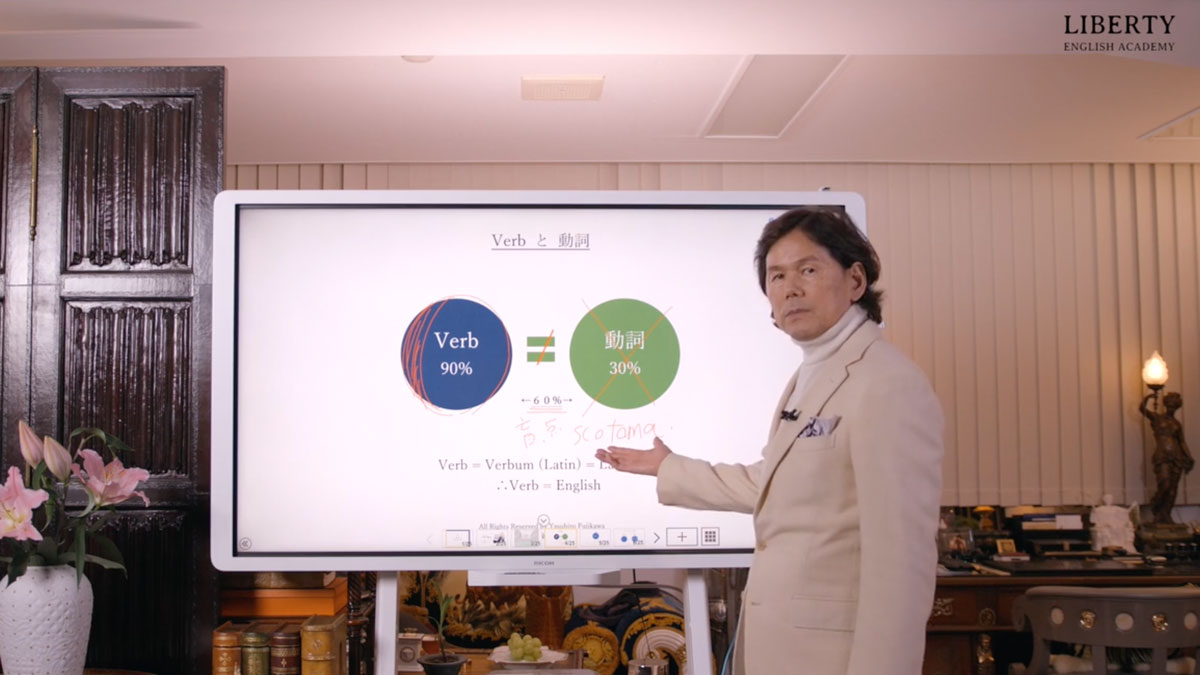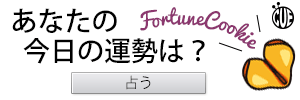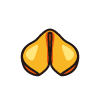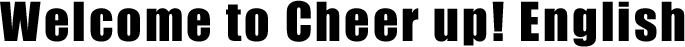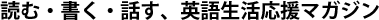IELTS ライティングの注意点 4
TOEFLとIELTSの違いを知って、試験に役立てよう!

IELTSライティング4つの評価基準のうち、前回と前々回で、「課題を満たす」にはどうしたらいいか具体的に解説しました。今回は、そこからCoherence & Cohesion (一貫性とまとまり)を作り出すにはどうしたらいいか見ておきましょう。
IELTSライティングで課題を満たすのが重要な理由
評価基準は4つあります。
Task Achievement (課題を満たしているか)
Coherence & Cohesion (一貫性とまとまり)
Lexical Resource (語彙)
Grammatical Range & Accuracy (文法知識の広さと正確さ)
ひとつの基準をうまくこなしたり、逆に捨てたりしたところで、4分の1にすぎないと思われるかもしれません。
しかし、「課題を満たす」以外の3つは、英語が得意な人でもなかなか完璧にはできないものです。語彙や文法で、試験当日ミスを0にするのは不可能に近いでしょう。
それに対して、与えられた条件を守りながら聞かれたことに答えることは、ある程度の英語力があればできるのではないでしょうか。
また、聞かれたことに真っ直ぐ答えることで、もうひとつの評価基準「一貫性とまとまり」も生まれやすくなります。
Coherence & Cohesion (一貫性とまとまり)をクリアするには
一貫性とまとまりのあるエッセイを書くには、それぞれの段落の役割を明確にすることです。
プランの段階で、書き出し、本論、結論を設定します。本論はさらに二段落くらいに分かれるでしょう。
段落はなんとなく「長くなったからそろそろ区切ろう」などと切るのではなく、あらかじめどの段落に何を書くか決めた後で書き始めてください。
ひとつの段落にひとつの内容を書くという原則を忘れないようにしましょう。さらに、段落の最初で内容をリードする一文を書き、次いでそれを詳しく説明するように続けると、読む人に分かりやすくなります。
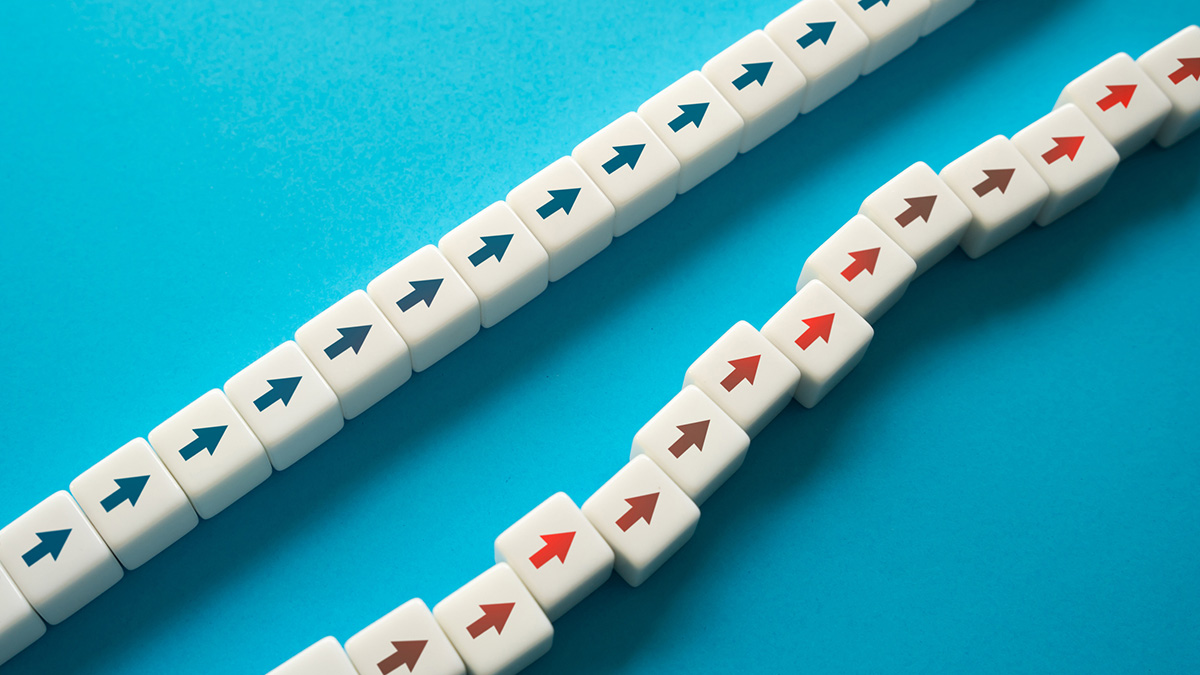
つなぎの言葉
段落の役割を明確にしたら、それぞれの段落を結ぶ「つなぎの言葉」を考えます。
その際、順接ならいつもtherefore(したがって)、逆説ならいつもhowever(しかしながら)ではなく、同じ意味のさまざまな言葉を覚えておくと便利です。
英語の文章は繰り返しを嫌うので、短いエッセイの中に同じ「つなぎの言葉」を使わない方がいいですね。
たとえば、thereforeの代わりにhence(このようなわけで), thus(結果として)なども使えるようにしておきましょう。逆説なら、nevertheless(そうは言っても)などもあります。
また、接続詞や接続副詞など一語の言葉だけではなく、as a result(結果として)、in contrast(それにひきかえ)などの表現も練習しておくことをお勧めします。

| ライタープロフィール●外国語人 | |
 |
英語、フランス語、外国語としての日本語を教えつつ、語学力に留まらない読む力、書く力を養成することが必要であると痛感。ヨーロッパで15年以上暮らし、とりあえず帰国。この世界の様々な地域で日常の中に潜む文化の違いが面白くて仕方がない。子育て、犬育て中。TOEIC®985点 |